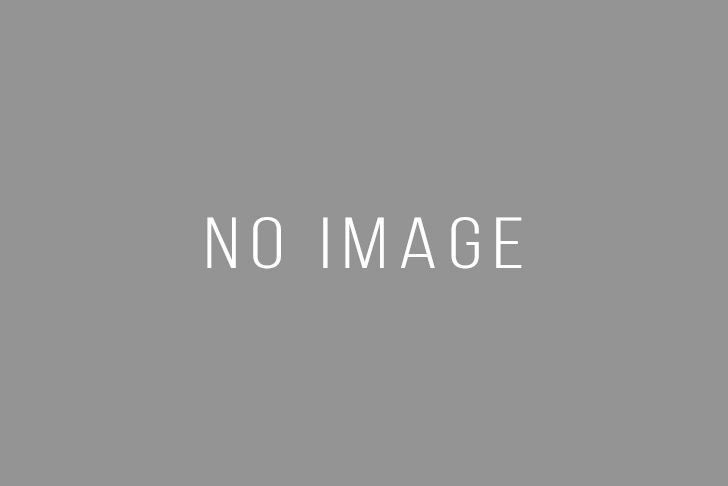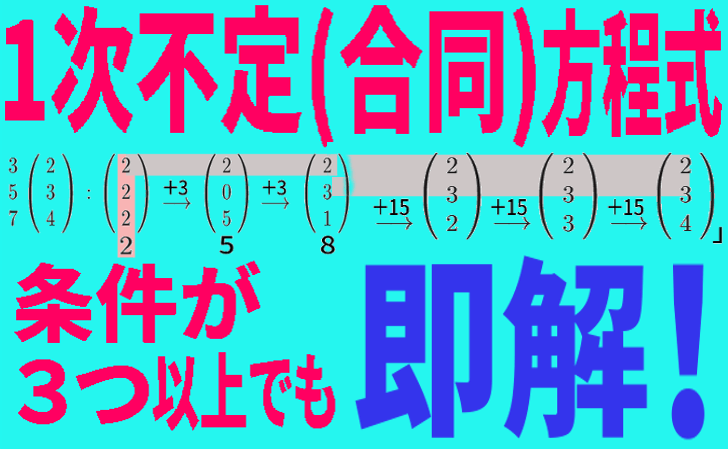辞書型配列【DNCL拡張版の話】
配列またはリストと呼ばれるデータ形式のことは、既に学習してきました。
例えば Hi=[ 10, 20, 30 ] という配列だとすれば、Hi[ 0 ] が 10、Hi[ 1 ] が 20、Hi[ 2 ] が 30 を表します。
[ … ]の中の 0, 1, 2 が、何番目の要素であるかを表す 添字(インデクス)です。
いわば配列とは、添字という番号 0, 1, 2 (0番から始めます。注意!) に対して 値(10, 20, 30 など)を対応させるもの だといえます。
それでは配列を使って、次の問題の解決を考えてみましょう。
米ドル | ユーロ | ポンド | 豪ドル |
143 | 155 | 186 | 95 |
配列には添字(インデクス) というものがあり、
添字\(\mapsto\)各要素 という対応によって、
何番目の要素のことか を決めています。
DNCL 普通の配列で対応づけ
関数定義 レート( tuuka_in ):
# 2つの配列(要素数同じ!)を用意する
Tuuka = ["米ドル","ユーロ","ポンド","豪ドル"]
Kawase = [143, 155, 186, 95]
iを0から3まで1ずつ増やしながら繰り返す:
もしTuuka[i]==tuuka_in ならば:
soeji_in = i #その添字をセット
戻り値( Kawase[soeji_in] )
表示する(50 * レート( "ユーロ" ))
のように記述するところを
変数の初期設定
Tuuka = [“米ドル”,”ユーロ”,”ポンド”,”豪ドル”]Kawase = [143, 160, 186, 95]
DNCX 辞書型配列と一般列挙
関数定義 レート( tuuka_in ):
# 通貨→為替 対応の 辞書型配列
T_K_taiou= {"米ドル":143 ,"ユーロ":155 ,"ポンド":186 ,"豪ドル":95 }
# T_K_taiou["米ドル"] は 143 , ... のようになる!
sをT_K_taiou.キー集合() から順次出しながら繰り返す:
もし s==tuuka_in ならば:
戻り値( T_K_taiou[s] )
戻り値(1) #キーになかった場合
表示する(50 * レート( "ユーロ" ))
のように記すことができます。
config.yaml
key: valueその場合、
OUT_RESULT
[0, 2, 4, 6, 8]Done in 0.123s注意点ですが、
{ キー1 : 値1 , キー2 : 値2 , \( \dotsm \) , キーN : 値N }
ここが とても大事 です。